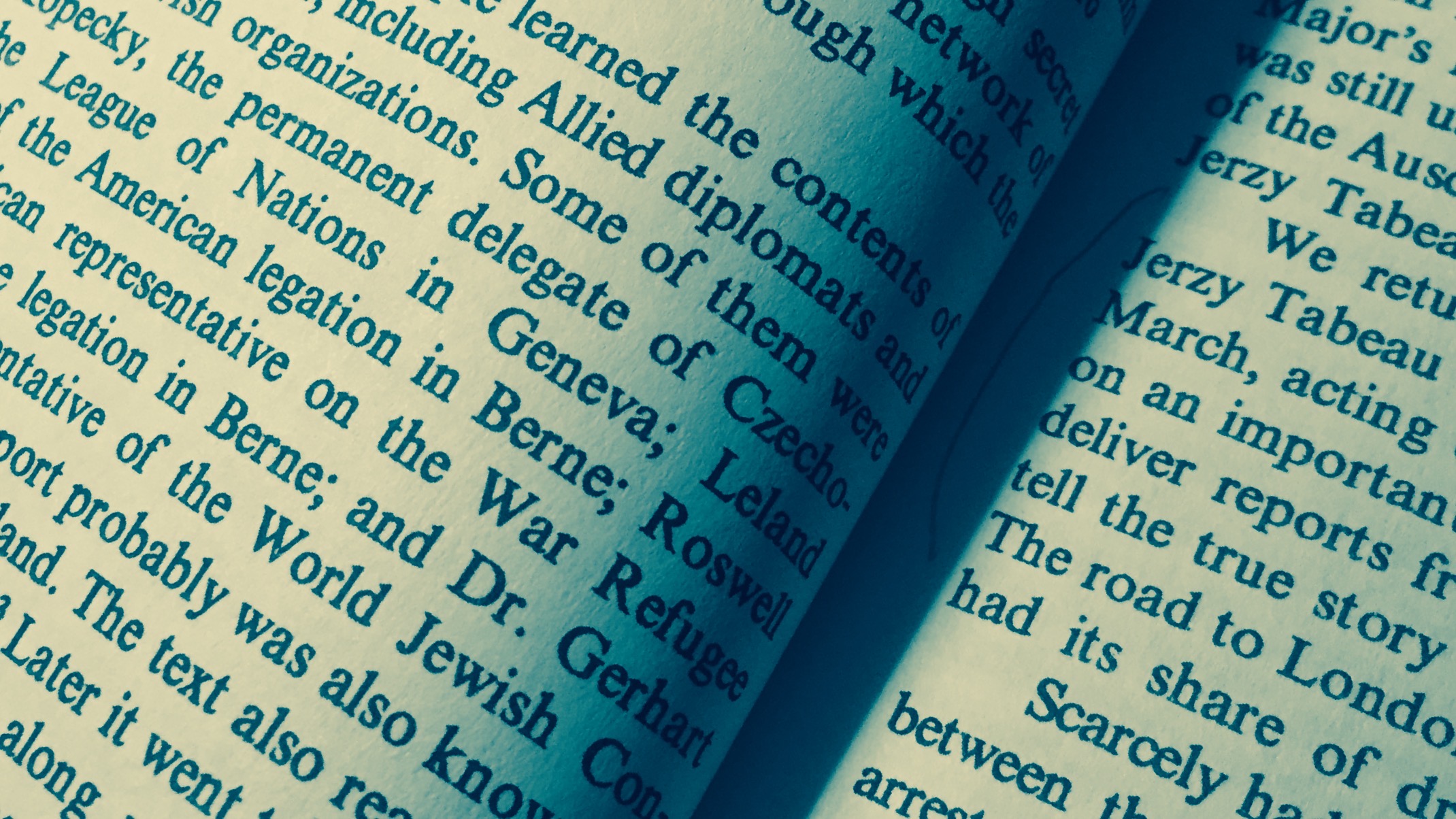なぜ人は書くのか
なぜ人は書くのだろうか。なぜ人は言葉を綴るのだろうか。日々の業務でもなく、学生の課題でもなく、誰にも命じられているわけでもなく、自発的に書かれる言葉がある。なぜ暇な時間に、わざわざ書くのだろうか。
「言葉の外へ」の作者は保坂和志さん。小説を書いている。「試行錯誤に漂う」も読んでいたが、なんとなく「言葉の外へ」に手を伸ばしたら、先にこちらを読み終わってしまった。
小説にせよ、あるいは劇にせよ、映画の脚本にせよ、それらが書かれるのは、何かそこに伝える価値のあるものがあるからだと、その書き手たちが考えているからでしょう。
誰もが知っていることは、きっと書かれない。「1+1=2」ということだけが書かれた本は、たぶん、ないだろう。みんながすでに共有していることからだ。だから、人が書くのは「私は知っていて価値はあるのだけれども、みなが知っているわけではないこと」なのかもしれない。
「ものと言葉」、「出来事と言葉」「言葉と言葉」。その一つ一つが変わらないとしても、それらがどのようにして(ある人の中で)互いに連なりあっているかが、その人を現すのだと思う。
少し抽象的なので、具体的に示してみよう。例えば「朝日新聞」という言葉があります。この「朝日新聞」という言葉に、どのような言葉が連なるだろうか。「リベラル」「言論の自由」という言葉が連なる人もいるだろうし、「左翼」「偽善者」という言葉が連なる人もいるでしょう。あるいは、新聞など関心はないから「特にイメージはない」という言葉が連なる人もいるでしょう。
どれが良いとか悪いとかいうことではなく、ある言葉(ここでは「朝日新聞」)に、どのような言葉が連なるかが、やっぱりその人を現すのです。
小説はまさに、言葉と言葉の連なりそのものです。言葉と言葉がどのように連なっているかは、一人一人で違います。まさに十人十色でしょう。小説家は、その小説において、ある一つの言葉と言葉の連なりの体系を示します。言葉と言葉がどう連なっているかは、まさにその人の世界観であり、人間観です。
小説家は、その小説において自らの世界観、人間観を、世界に向かって提案しているのかもしれません。「このような世界観、人間感を持ってみてはいかがでしょうか」と。新しい世界観、人間観を持つようになれば、人の生き方は変わり、人生が変わることになるでしょう。
優れた小説は、その読者における「言葉と言葉」の連なりを揺らして、その変容を促すことになるのでしょう。もし、ある小説(劇、映画・・・)がその読者の「言葉と言葉」の連なりを揺らしたのであれば、それはその読者を変えたことになるのでしょう。読者が、小説を読むのも、何か新たな「言葉と言葉」の連なりを求めているからなのかもしれません。
できる限り多くの疑問や仮説を出して、作者と読者がこの世界を限定して見ないようにする場所に連れていくもの、それが小説だ
「言葉の外へ」 保坂和志 河出書房新書 2012年 p.193
伝えようとしない言葉は?
でも、ちょっと待ってくれという反応もあるかもしれない。公表することを考えていない小説、あるいは誰にも見せるつもりのない日記はどうなのかと。それも「将来の自分」という他人を読者に想定していると言えることもないかもしれない。だけれども、本当にそんなことも考えずに、発作のように書かれる言葉もある。そんな言葉はなぜ書かれるのだろうか。
というより、もう答えは書いてしまっている。そのような言葉は「発作」として書かれる。つまり意図的に書こうとして書いているわけではない。イメージとしては歯磨きチューブに強い圧力をかけると、歯磨き粉が飛び出してくるような感じだろうか。その圧力が喜びなのか、悲しみなのか、怒りなのか、恨みなのかは分からないが、とにかく押し出されて出てくる歯磨き粉のように、それらの言葉は勝手に飛び出てくる。熱いものに触れたら咄嗟にそれから離れるように、その言葉は自動的に出てくる。
全力をこめて伝えようとしている人間はそれ自体が現象なのだ
「言葉の外へ」 p.4
何かを伝えようとしている、その人自身が一つの現象なのであり、一つの意味を持つのです。言葉には「論理的意味」と「存在的意味」があります。「論理的意味」はまさにその言葉が、どこで誰が発したり、書いたりしても有する意味。「存在的意味」はまさにその言葉が、ある特定の場所で、特定の人によって発されることで有する意味。
例えば、教師が間違った説明をしているといときに、その答えを訂正するような学生の言葉で考えてみると「論理的意味」は、正しい答えそのものが教科書に書いてあっても意味するもの。「存在的意味」はその学生が、教師を皆の前で間違いを指摘する勇気を持っているという意味です。
喜びの言葉や怒りの言葉が伝わってくるのは論理的意味もありますが、存在的意味も大きいように思えます。それこそ言葉になっていないような叫び、つまり論理的意味はないといっていい言葉が、喜びの言葉なのか、怒りの言葉なのかなんていうのは、存在的意味を通じて伝わってくるわけです。
何かを伝えようとしている、その人自身、さらにいえばその小説自身(劇自身、映画自身…)が、一つの意味を持ちます。そして、この存在的意味は、その言葉を発する人などが意図的にその場でつくることができないものです。まさにその人が、それまでの人生で何を考えてきたのか、どのように生きてきたのかが、そこに現れます。
「言葉の言葉」の連なりがもつ論理的意味ではなく、「言葉の言葉」の連なりがもつ存在的意味が、その人自身なのです。そう考えてみると、日々の対話とは、まさに「言葉と言葉」の連なり同士が互いを揺らしあうことなのかもしれません。
それで、なぜ人は書くのか?
最初の問いに戻りましょう。なぜ人は書くのでしょうか。特に小説であったり、劇であったり、書く必要性はないのに書かれるものは、なぜ書かれるのでしょうか。
きっと上で書いてきた「私は知っていて価値はあるのだけれども、みなが知っているわけではないこと」を伝えたいという思いと、「発作」の2つが理由のような気がします。「発作」と言っても瞬間的な発作ではなく、慢性的な、極めて息の長い「発作」ではありますが……
そのようにして小説を書いているとき、小説家は、自分が書いているとも言えるし、あるいは書いていないとも言えるというように感じるのではないでしょうか。何かに突き動かされて、これを書いているのだという感覚を持つこともあるでしょう。
愛や真実、真理を主題にした小説を書くとき、それはなかなか意図的に書くことは難しいように思えます。小説の登場人物に何かを語らせようと強く意識しすぎると、どこかで嘘が生まれるように思えます。何かが、作者を突き動かして、登場人物に喋らせることに成功したとき、その言葉は論理的意味だけでなく、存在的意味においても愛を語ることに成功するのでしょう。
だから「なぜ人は書くのか」という問いに対する答えは(それが小説などであれば)、そもそも書いていないということになるのかもしれない。質問に答えていないという気もするが、まさに、これが答えなのだと思う。それはいつの間にか、書かれているのだ。
気がついたら書かれていたというのが、本当のところだろう。なぜりんごが落ちるのかと言われても困る。りんごは落ちるのだ。そういうことにこの世はなっている。価値のあるものを共有したいという思うと、人は自然に書いているのだ。なぜりんごは落ちるのか?落ちるから。なぜ人は書くのか。書くから。
そのような言葉は、きっと、人が書いているのではなくて、言葉が人を介して自らを表していると言えるのでしょう。人がペンを使って文字を記すように、言葉は人というペンを使って自らをしるす……そんなイメージです。
言葉が人を通して、自らを現しているような文章。いや、「ような」ではないだろう。言葉が人を通して、自らを現す文章。そのような文章こそが人を感動させるのだろう。
少し敷衍していえば、そのようにして、言葉を自らの体を通して表現させられるような役者こそが、人を感動させられるのだろう。その時、その役者は何かを演じているわけではなく、その言葉そのものになっている。だから、その役者は、人を感動させられるし、場合によっては、優れた小説と同じように、人と社会を変えることもできるのだろう。音楽もそうだろう。音楽がその演奏家を通して自らを表現するようなとき、その音楽は人を動かすのだろう。画家もそうだろう。絵画がその画家を通して自らを表現したような絵画…例はいくつでも挙げられるのだろう。
最後に答えるとすれば、なぜ書くのか?それは、言葉は自らを言葉として表そう、現そうとするから。こういう答えになるのでしょう。