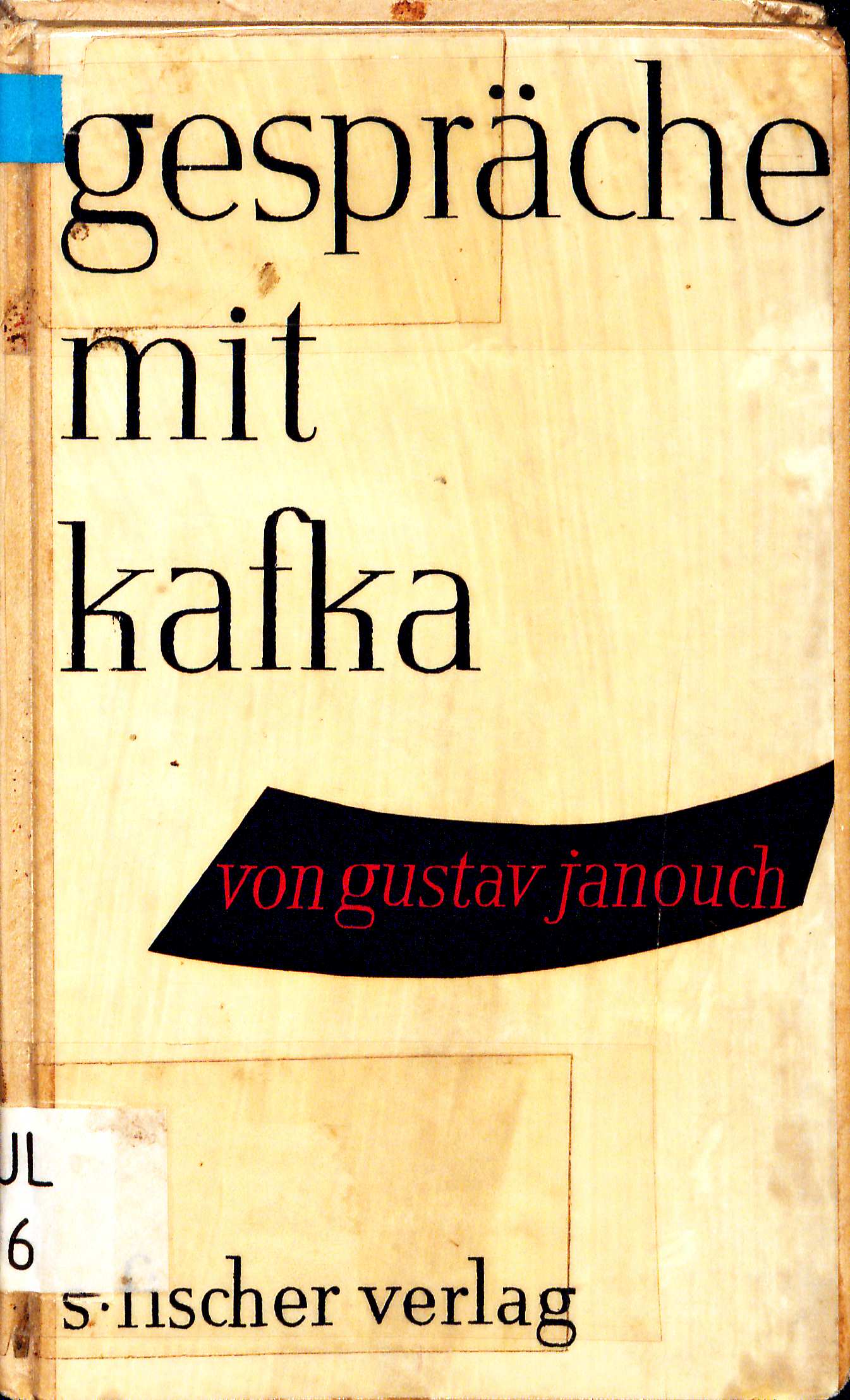カフカとの対話 手記と思想
『カフカとの対話 手記と思想』(1951)は、フランツ・カフカ(1883-1924)との対話を、同じくチェコの作家グスタフ・ヤノーホ(1903-1968)が記した本。カフカといえば、主人公のザムザが朝起きたら虫になっていた『変身』(1915)や、理由も分からないままに訴追されるヨーゼフ・Kが主人公の『審判』(1925)などが有名だろう。もちろん、いつまでも城の中に入ることができないKが主人公の『城』(1926)も代表作の一つであろう。
このカフカとの対話を読んで分かったことが3つあった。1つ目はカフカは優しい人であったということ。2つ目はカフカが自らの作品を焼き捨てようとしていた理由。3つ目はカフカが書くことに賭けていた思いだ。簡潔に書いてみよう。
カフカの優しさ
一人の人間に他の人間の言うことが分からないとすれば、彼はおそろしく滑稽なのではなく、孤立し、貧しく、そして見捨てられているのです
『カフカとの対話 手記と思想』 グスタフ・ヤノーホ みすず書房 2012年 p.98
これは言葉が相手に伝わらないときに、どう思うかという話だ。話が分からない人のことを馬鹿だとか、阿呆だとか思うのは楽だ。だけれどもカフカのこの言葉は、そうは考えていない。言葉が分からないということは、それは、その言葉の分からない人が、どこか陸の孤島に暮らしているということを意味している。言葉が分からない人は「孤立し、貧しく、そして見捨てられている」。そうであるのならば言葉が伝わらない相手を「滑稽」にするのは酷い話だろう。どうして言葉が伝わらないのか、どのように言葉を発すれば、その人と言葉を分かち合うことができるのかを考えるのが優しさなのだろう。
作品を焼き捨てようとした理由
カフカの作品は不条理小説と呼ばれる。そんな簡単な言葉でカフカの作品を表現することを否定する人もいるようだけれども、やはり、不条理を書き表そうとしているという指摘が完全に間違っているということもないのだろう。
われわれをここまで導いて来た道は跡形もなくなりました。それとともにこれまでの共通な未来の見通しも、すべて消えてしまいました。われわれが体験するのはまず希望もなく突進するくらいのことにすぎません。窓から外を見れば世界が眺められます。どこへあの人たちは去って行くのか。なにを望んでいるのか。われわれはもののもつ超個人的な意味の連鎖をもはや知ることはできない。雑沓のなかで、しかもめいめいが黙って自分のなかに孤絶するのです。世界の評価と自分の評価との間もうまく噛み合わなくなっているのです
pp.168-169
ヤノーホとカフカが出会ったのは1920年とされています。第一次世界大戦が終わった直後です。この時代を生きた人々の価値観は激しく動揺していました。17世紀を端緒とする理性主義は数千万人の死者を出した戦争によって死刑宣告を下されました。一方で理性主義によって生み出された近代科学のもとでは、神を信じることもかつてのように容易なことではなくなっていました。一体、どこに確固とした、頼りにできる価値を見出すことができるのか。全てに価値を与える神は消え去り、「もののもつ超個人的な意味の連鎖をもはや知ることはできな」くなってしまいました。確固とした存在、意味を与えてくれる羅針盤は消え去りました。
「しかし確実さがないとすれば、それでは人生のすべてはなんでしょうか」
p.207
「それは失墜です。おそらく、それは堕罪です」
「罪とはなんでしょうか」
カフカは答える前に、舌先で下唇を濡らした。
「罪とはなにか……私たちはこのことばとそれを用いる術を知っています。しかしその実感と認識は失われてしまった。おそらく、それは劫罰、神の失踪、意味の喪失にほかなりません」
カフカはこのような意味の喪失という苦しみに向かいあうなかで自らの小説を書いていったのでしょう。カフカは暇つぶしで小説を書いていたわけではなく、日々、自らが直面している苦悩を小説のなかで捉えて、理解しようとしたのでしょう。
そしてカフカは詩人の役割について以下のように語っています。
しごく明瞭なことです。詩人は、現実を変更しようとして、人間に別な眼を嵌めようとします。したがって彼らは元来国家にとっては危険分子です。彼らは変革しようとするのですから。国家とともにそのすべての恭順な下僕たちは、つまりただ持続することだけを望んでいるのです
p.230
カフカは詩人の役割とは「人間に別な眼を嵌めよう」とすることだと述べています。ただカフカの小説では、何らかの答えが与えられているようには思えません。カフカは自らの絶望を記した小説を「袋小路」のようなものだと言っています。
助けることのかなわぬとき、人は黙らねばなりません。決して自分の絶望によって、患者の容態を悪化させてはいけない。だから私のなぐり書きはすべて廃棄しなければならないのです。私は光ではない。私は自分の茨の茂みに踏み迷ったのです。私は袋小路です
p.246
カフカは自らの作品は「袋小路」のようなもので、意味の喪失という重病にかかっている患者の容体を良くすることはできないと考えていました。むしろ場合によっては、患者の容体を悪化させてしまうことだってありえるのではないかと考えたようです。だからこそ、彼は自らの作品を焼き捨ててくれと頼んでいたのでしょう。
「言葉の外へ」でも書いたことと重なりますが、小説とは、一つの「言葉と言葉の連関の新たな宇宙」です。目の前に広がる現実世界とは異なる言葉と言葉の連関のあり方、つまりは、新たな社会のあり方を、人間の存在の仕方を提起する、一つの宇宙です。カフカは、自身の作品は、そのような新たな宇宙を作り出せていないと考えたのでしょう。そうであるのならばわざわざそれを出版する必要もないし、燃やしてしまえばいい。カフカの思考回路はこのようなものだったのでないでしょうか。
書くこととは
カフカにとっては書くとは暇つぶしではなく、彼の存在そのものであったのでしょう。
芸術とはつねに全人格の関与です。芸術が究極において悲劇的であるのはそのためです
p.76
書くことはカフカにとっては、それを生きることも求めるものでした。「なにかをただ語るというのでは足りない。人はものを生きねばなりません」(p.229)という言葉もそうですし、キルケゴール批判のなかにもその思いは見受けられます。
キルケゴールは、存在を審美的に享受するか、倫理的に体験するか、この問題に直面します。が、私にはこの設問は誤りだと思われます。あれかこれかはゼーレン・キルケゴールの頭のなかにあるにすぎない。事実は、存在の美的享受というものは、謙虚な倫理的体験を通してのみ達せられるものです。これはしかし、一時的な私見にすぎないので、さらによく調べれば、おそらく私は撤回するでしょう
p.133
これはキルケゴールの言い方も、カフカの言い方もどちらも正しいと言えるのではないでしょうか。ただ眺めるだけで済むような美は、本物の美ではない。自らに美を実行させるような美こそが本物の美である。キルケゴールは前者の美にも便宜上「美」という名前を与えたが、後者の「美」こそが求められているのだと考えました。カフカは前者は「美」の名に値するようなものではなく、後者だけが「美」の名に値するのだと考えたのではないでしょうか。とりあえず、そう理解してカフカとキルケゴールにここでは握手をしてもらいましょう。
さて、本書の序文でカフカはヤノーホに「人は、どうあっても書かねばならぬものだけを、書かねばなりません」(p.9)と語ったことがあると記されています。カフカのこの言葉をうけてヤノーホはこう述べています。
書く、ということは、それが真の価値をもつ以上、解放の行為であります。人は個人の地平の枠を破って、超個人的な、だからそれだけより深い人間存在の視野に到達しようとするのです
p.9
カフカは自らに課した厳しい基準を自らの作品が乗り越えていないと考えたのでしょう。だからこそ、彼は彼の作品を焼き捨ててほしいと願ったのかもしれません。焼き捨てるということは、カフカ自身の書いたことを実行するということでもあったのでしょう。
友人であるマックス・ブロート(1884-1968)によって、その願いは実行に移されることなく、今でも私たちはカフカの作品を読むことができます。カフカの願いが実行されなかったことがカフカにとって本当に良いことだったのかどうかは分かりません。ただ、その焼き捨ててくれと願ったカフカの思いのなかにこそ、カフカの存在の核があるのでしょうし、カフカの人間としての心髄があるのでしょう。